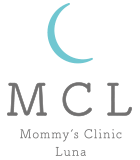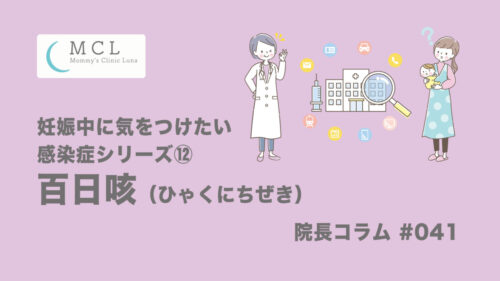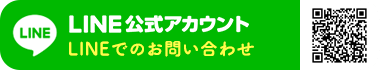妊娠中に気をつけたい感染症シリーズ⑫:百日咳 院長コラム#041
2025.05.05 院長コラム
院長の吉冨です。今回は妊娠中に気をつけたい感染症シリーズ第12回目、百日咳についてです。感染者の増加や乳児における重症例や抗生剤が効きづらい例の増加などの報道が最近増えており、お問い合わせを多くいただくため、よく聞かれる内容を中心に簡単にまとめてみました。
百日咳とは
百日咳とは百日咳菌に感染して発症する急性の呼吸器感染症です。咳が治まるまで約100日間と長い時間がかかることから、百日咳と呼ばれています。予防接種で防ぐことができる感染症ですが、ワクチンを接種していてもかかることはあります。また、ワクチンの効果が薄れてしまった大人も感染します(子どもの頃に予防接種を行うため、大人になると効果が弱まってしまいます)。特に乳幼児は重症化することがあるため注意が必要です。感染経路は、感染している人の咳やくしゃみなどのしぶきから感染する「飛沫感染」と、菌で汚染されたものに触れることで感染する「接触感染」です。感染力はかなり強く、インフルエンザやおたふくかぜ(ムンプス)よりも数倍感染力が強いと言われています。
症状
症状は「カタル期」、「痙咳期(けいがいき)」、「回復期」と変化していき、症状発現までは5~10日の潜伏期間があります。カタル期は、軽い咳や鼻水、くしゃみなど風邪とほとんど症状が変わらないため診断が難しいのですが、最も感染力が強いのがカタル期です。痙咳期は、カタル期よりも咳が強く、特徴的な咳が出ます。コンコンと激しい咳が続いた後、ヒューっと息を吸い込む音を繰り返します。乳児の場合、突然息が止まってしまうこともあるため、呼吸状態を注意深く観察する必要があります。大人は百日咳の特徴的な咳が出ないことも多く、感染に気づかないまま周囲に感染を拡大させてしまうことも少なくありません。
治療
治療にはマクロライド系と呼ばれる抗生剤が有効で、妊婦さんにも安全に使える抗生剤です。抗生剤を使用した数日後には百日咳菌を周囲にうつすことはなくなりますが、咳は落ち着くまで時間がかかります。近年、マクロライド系抗生剤の耐性菌が増加していると問題になっています。
予防
予防接種を受けると百日咳にかかるリスクを80~85%程度減らせると言われています。予防接種は現在では生後2ヶ月から接種可能となっています(2023年4月から改訂されている)。大人は感染しても軽症で済むこともありますが、乳幼児では感染すれば重症化するリスクが高い感染症ですので予防はとても重要です。こどもへの感染を防ぐために、周囲の人が手洗いやうがい、マスクなどの基本的な感染対策もしっかりと行うことも大切です。
妊娠中の対策
上記で説明したように、百日咳は感染力が強く、乳幼児(特に生後6ヶ月未満)に感染した場合に重症化するおそれがあります。しかし、百日咳含有ワクチンの定期接種は生後2ヶ月以降に行われており、それでは接種前の乳児の感染を防ぐことはできません。そこで近年、妊婦さんにワクチンを接種し、母体に免疫(抗体)を作ってもらい、その抗体を胎盤・臍帯を通して胎児に送り届ける「母子免疫ワクチン」が脚光を浴びています(妊娠中に気をつけたい感染症シリーズ⑧:RSウィルスでも母子免疫ワクチンについて説明しています)。
ワクチンについて
成人に接種できる百日咳含有ワクチンは主に2種類あります。
小児用に開発された定期接種用3種混合ワクチンDTaP(トリビック🄬)と海外製の成人用のTdap(boostrix 🄬)です。どちらのワクチンもジフテリア(Diphtheria)、破傷風(Tetanus)、百日咳(Pertussis)が含まれており、DTaPやTdapはこれらの頭文字を指しており、3種混合ワクチンと呼ばれます。
DTaP(トリビック🄬)
定期接種用3種混合ワクチンDTaP(トリビック🄬)は国産ワクチンで、もともと小児用に開発されましたが、2018年から成人にも接種適応が拡大されており、不活化ワクチン(毒性や感染力なし)であることから妊婦さんも接種が可能で乳児への抗体移行も確認されています。しかし、現時点では、DTaP(トリビック🄬)は乳児の百日咳の重症化予防効果は証明されていません。また、成人に対してはジフテリアトキソイドの成分量が多く、接種部位の腫れや発熱などの副反応が多いと言われています。
Tdap(boostrix 🄬)
グラクソ・スミスクライン(イギリス)による成人用の3種混合ワクチンです。欧米諸国で百日咳の母子免疫ワクチンとして推奨されている成人用3種混合ワクチンですが、現時点では日本で認可されていません。そのため、個人輸入などで取り扱っている施設があります。世界的に使用されているため、妊婦さんへの接種に対するエビデンスはDTaP(トリビック🄬)より多いです。また、ジフテリアトキソイドの成分量が少なく、DTaP(トリビック🄬)よりも腫れにくいと言われています。諸外国のガイドラインでは、妊娠27~36週での接種が推奨されています。注意すべき点は日本で薬事承認がされていないため、万が一、ワクチンによると考えられる副反応や後遺症が発生した際に、国のワクチン副反応救済制度を使用できない可能性が高いということです。
最後に
RSウイルスワクチン(アブリスボ🄬)は、昨年から母子免疫ワクチンとして積極的に推奨されるようになりました。現在、厚生労働省や各学会などから、母子免疫ワクチンを目的とした妊婦さんへの積極的な百日咳含有ワクチンの接種を推奨するような声明はありませんが、今後、変更してくる可能性はあるかと思います。
上記でも説明しましたが、諸外国ではエビデンスをもとに母子免疫ワクチンを目的とした妊婦さんへのTdap(boostrix 🄬)の接種を推奨しています。日本ではTdap(boostrix 🄬)が認可・販売されていないため、母子免疫ワクチンを目的とした妊婦さんへの百日咳ワクチン接種の実現可能な代替案としてDTaP(トリビック🄬)の活用が考慮されますが、現時点では、妊婦さんへのDTaP(トリビック🄬)接種による乳児の百日咳の重症化予防効果は証明されていないことはおさえておく必要があります。
現在、当院ではDTaP(トリビック🄬)の取り扱いはしておりませんが、妊娠中にDTaP(トリビック🄬)接種をご希望される場合は、妊娠27~36週頃(諸外国での接種推奨の妊娠週数)に、小児科や内科クリニックにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。また、厚生労働省の感染経路の調査を参照してみますと、乳幼児の両親や祖父母など育児に携わる方々も接種の対象となりえるかもしれません。
他の感染症と同様に産婦人科には感染に弱い妊婦さんが多くいらっしゃるため、症状がある場合は産婦人科の受診はせず、内科や耳鼻科などで診断・治療を受けてください(その際、かかりつけの産婦人科へは診療時間内にお電話で報告いただけると良いかと思います)。
以上、簡単に産科医からの視点で百日咳について解説してみました。
百日咳に関して、ご心配やご質問などがある場合はかかりつけ医にお尋ねください。