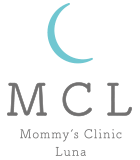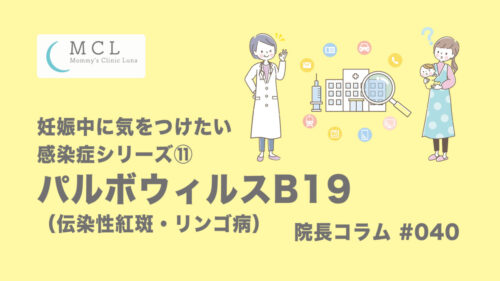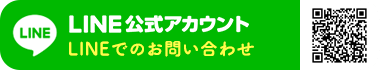妊娠中に気をつけたい感染症シリーズ⑪:パルボウィルスB19(伝染性紅斑・リンゴ病) 院長コラム#040
2025.04.14 院長コラム
院長の吉冨です。今回は妊娠中に気をつけたい感染症シリーズ第11回目、パルボウィルスB19についてです。妊娠中は特に注意が必要な感染症です。
パルボウィルスB19とは
パルボウィルスB19と言うとなんだか難しい病気かな?と思われるかもしれませんが、一般的にリンゴ病(伝染性紅斑)といわれる病気を引き起こすウィルスです。症状としては大人と子供で違いが出てくることが多いです。子供が感染した場合、高率にほっぺが赤くなったり(リンゴ病と言われる所以)、熱が出たり関節が痛くなったりという症状が出ます。大人が感染した場合は風邪のような症状が出ることがありますが、約半数は症状のない不顕性感染といわれています。日本においては妊娠可能年齢女性の約半数が免疫(抗体)を持っていると推定されています。免疫を持たない妊婦さんの約1%が妊娠中に感染するといわれており、流行期には約10%が妊娠中に感染するといわれています。家族内で誰かが発症したり、職場内で流行したりすると感染リスクが高くなるため、小さなお子さんをお持ちの方や保育園や幼稚園の先生、医療従事者などは特に注意が必要です。
感染経路は飛沫感染や接触感染で感染力は強いです。感染が成立した場合1週間前後の潜伏期間を経て、5日間程度のウィルス血症(周囲への感染力が強い時期)となりウィルス血症が改善した頃に症状が発現します。つまり、感染が成立してから2週間ほどで症状が発現しますが、症状が出たころにはウィルス血症は改善しているため、周囲への感染力はなくなっているというのが特徴で、症状が出たときにはすでに周囲へ感染が拡大している可能性が高いと考えます。そのため、発症者と妊婦さんを隔離しても有効な予防とはなりません。
妊娠中にパルボウィルスB19に感染したらどうなるの?
パルボウィルスB19は胎盤を通過しておなかの中の赤ちゃんに感染し、胎児水腫(おなかの中の赤ちゃんにとって重篤な状態)を引き起こす可能性があります。非免疫性胎児水腫の原因の10~30%程はパルボウィルスB19の感染であると考えられています。妊婦さんがパルボウィルスB19に感染すると、20~30%程がおなかの中の赤ちゃんに感染し、約3%が胎児水腫を生じるとされています。胎児水腫に至るまでの期間としてはほとんどが母体感染から8週間以内(中央値:3週)で、8週を超えたら胎児水腫に至る可能性は低いです。また、感染成立時期が20週未満であれば約13%が流産や胎児死亡に至るのに対し、20週以降であればそれらの出来事は0.5%と確率はかなり低くなります。
パルボウィルスB19の感染が疑われる妊婦さんへの対応
家族内や職場で発症者が確認された場合、前述の通りすでに感染が拡大し、妊婦さんも感染してしまっている可能性があります。妊娠中に感染しても必ずしもおなかの中の赤ちゃんに感染する訳ではありませんが、感染の有無は確認しておく必要があります。検査としては妊婦さんの血液検査となります。パルボウィルスB19-IgMとIgG検査を同時に行うことが一般的かと思います。IgMは保険が適用されます。潜伏期があるため接触後10日以降のできるだけ早い時期に検査を行うのが良いです。IgMは感染から2~3ヶ月で陰性化することが多いですが、6ヶ月ほど陽性となる場合や偽陽性となることもあります。IgGは保険が適用されません。IgMが陽性化した後、数日遅れてIgGは陽性化します。IgGは終生免疫のため、一度感染したらその後は一生陽性であることがほとんどです。以上のことから、IgM陽性・IgG陰性となれば感染からかなり早い段階であることが示唆されます。IgM陽性・IgG陽性の場合は数ヶ月以内の感染が示唆されます。IgM陰性・IgG陽性の場合は昔の感染を示唆し、おなかの中の赤ちゃんには影響しないと考えられます。IgM陰性・IgG陰性の場合は感染していないか、感染後ごく初期であると考えられるため、2~4週間後に再度検査する必要があります。
ここで重要なことが2つあります。1つ目は感染者と接触した時期をできるだけ詳細に把握しておくことです。感染した時期がはっきりしていると検査の精度があがりますし、赤ちゃんへの影響を推定するのに大いに役立ちます。2つ目は妊婦さんへの感染が疑われる場合、まずはかかりつけの産婦人科へ電話で相談することです。産婦人科は妊婦さんの多い場所であるため、何の前触れもなく受診すると他の妊婦さんへの感染を引き起こす可能性がありとても危険です。病院のスタンスによるかもしれませんが、内科などで検査をしてもらい、結果を知らせて欲しいとする場合と、他の患者さんがいないときに受診を指示し検査を行ってくれる場合とがあるかと思いますので、指示に従ってください。また、電話でのお問い合わせは緊急を要する事案ではないため、診療時間内に問い合わせをしてください。
妊娠中の感染と診断されたら
前述しているとおり、妊婦さんが感染したからといっておなかの中の赤ちゃんが必ずしも感染しているとは限りません。また、赤ちゃんが感染していたとしても悪影響が必ずしも顕在化する訳ではないため、過度に心配しないようにしてください。パルボウィルスB19が胎児水腫を起こす要因は赤ちゃんの重度の貧血を引き起こすことで生じます。そのため、妊婦さんの感染が判明した場合、赤ちゃんの貧血の程度や胎児水腫の発生がないか注意深く見ていく必要があります。いずれも超音波検査で推定や観察ができるため、針を刺したり侵襲的な検査を必ずしも必要とする訳ではありません。観察の期間は8週間前後で頻度は1-2週間に1度です。また、感染から2週間以上経過している場合は周囲への感染は起こらないため、通常の外来時間帯での診療で良いかと思います。
おなかの中の赤ちゃんの貧血が疑われたり、胎児水腫を認めた場合、おなかの中の赤ちゃんに輸血(胎児輸血)を行うという胎児治療が選択肢として出てきますが、実施できる施設は限られており、適応や評価なども十分に検討する必要があるため、周産期センターでの管理が必要となってきます。
最後に
現時点ではパルボウィルスB19のワクチンも治療薬も開発されていませんし、全妊婦を対象とした抗体のスクリーニングも推奨されていません。そのため、妊婦さんにとって最も重要なことは感染予防に努めることです。身近に発症者が出た時点ですでに感染している可能性が高いため、普段よりマスクを着用したり、手洗いを徹底するなどし、人混みを避け、感染情報に常にアンテナを張っておくことが重要だと考えます。
以上、簡単に産婦人科医からの視点でパルボウィルスB19について解説してみました。
パルボウィルスB19に関して、ご心配やご質問などがある場合はかかりつけ医にお尋ねください。